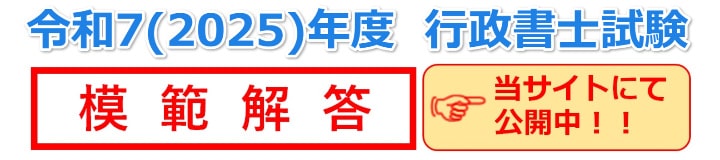- 行政書士になりたいけどどれくらい勉強する必要があるんだろう?
- いつから勉強を始めたら良いのかな?
行政書士を目指す方の中には、上記のようなことが気になっている方も結構多いのではないでしょうか。
もちろん必要な勉強時間や時期には個人差がありますが、合格を目指すならおよその学習時間と開始時期を知りしっかり対策を行う必要があります。
この記事では、行政書士試験合格に必要な勉強時間と最適な勉強開始時期について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
行政書士試験合格に必要な目安の勉強時間は?


行政書士試験は法令科目5科目・一般知識3科目の合計8科目、択一式・記述式合わせて60題を3時間かけて回答し、全体の6割以上点数を取る事ができれば合格となります。
簡単にまとめると以下の通りです。
- 全体得点 300点中180点(60%以上)
- 法令科目 244点中122点以上
- 一般知識科目 56点中24点以上
※難易度に応じて稀に合格点の調整が入ることもあります。
では、独学で勉強する場合や予備校・通信講座などで勉強する場合でどれくらいの勉強時間が必要なのか見ていきましょう。
独学で勉強する場合


まずは独学で勉強する場合です。ざっくりですが、独学で勉強する場合は500~600時間が目安の勉強時間と言われています。
しかし、平成18年度から試験制度が変更され難易度が上がったため、近年ではもう少し勉強時間を多く見積もる必要が出てきました。言い換えるともっと学習時間を増やさないと合格できなくなってしまったという事になります。
最近の合格者の声では、独学であれば800~1,000時間は勉強時間がないと厳しいと言う声が多くなっています。これを達成するには、1日3時間毎日勉強したとして、およそ9~11か月ほどの期間となります。
もちろん個人差はありますが、1年の大半を勉強に費やす覚悟が必要です。
予備校や通信講座を利用して勉強する場合


次に予備校や通信講座を利用して勉強する場合を見ていきましょう。
予備校や通信講座のホームページを確認すると、ほとんどの学校で目安の学習時間が掲載されていますが、これは学校によって結構違いがあります。なぜなら、学校のカリキュラムによってターゲットとする受講者のレベルが異なるためです。
例えば、法律に対しての知識が全く無い初学者の方と、法律の知識をある程度お持ちの法学部卒の方とではスタート地点が違いますからね。
各学校の初学者向けのカリキュラムで平均すると、通信講座では大体700~800時間で、通学型の資格学校ではおおよそ400時間程度で設定されています。
■各通信講座学習目安時間一覧
■各通学型資格学校学習目安時間一覧
| 資格学校名 | 目安学習時間 |
| 資格スクール大栄 | 230時間 |
| 東京法経学院 | 400時間 |
| LEC東京リーガルマインド | 410時間 |
| TAC | 420時間 |
ここだけ見ると、「通学型の資格学校の方が時間少なくていいじゃん!」と思うかもしれませんが、通信講座では自習時間や演習時間も込みのトータル時間になっておりますので、通学型の資格学校でも同等程度の時間が必要となるでしょう。
したがって、初学者が学校を利用して行政書士試験合格を目指すなら、700~800時間が妥当だと判断できるのではないでしょうか。
目安の学習時間を他資格と比較してみた


ここからは、行政書士の目安学習時間が他資格と比較してどの程度なのかを見ていきましょう。
以下に一覧表を作成しましたのでご覧ください。
■各通信講座学習目安時間一覧
| 資格名 | 目安学習時間 |
| 宅建 | 200~400時間 |
| 日商簿記2級 | 350~500時間 |
| 行政書士 | 700~800時間 |
| 社労士 | 1,000時間 |
| 司法書士 | 3,000時間 |
| 税理士 | 4,000時間 |
| 弁護士 | 6,000時間 |
一覧を見てみると、行政書士は簿記2級や宅建の勉強時間よりは多いものの、司法書士や税理士、弁護士といった超がつくほどの難関資格よりはかなり少ないのが分かります。
簡単にまとめると、一般的な資格よりはやや難しく、法律系の難関資格の中では易しい位置づけであると言えるのではないでしょうか。
行政書士は許認可申請書類をはじめ10,000種類以上を取り扱い、「書類のプロ」という別名がある程で、かなり需要のある職業となっております。
独占業務も有しており、その中で難易度も比較的易しいということであれば、法律系資格の取得を目指したいとお考えの方はまずは行政書士を目指すというのもアリだと思います。
実際、法律系の資格は試験範囲が被っている部分も少なからずありますので、法律系資格の取っ掛かりとしては非常に適していると思います。
行政書士試験合格に最適な勉強開始時期は?


行政書士試験は毎年11月に実施されており、それに合わせて勉強を開始する必要があります。
考え方を変えれば、年に1回しかチャンスはありませんので、勉強開始のタイミングを間違え不合格になった場合、リベンジするまでもう1年後回しになってしまいます。
では、いつ試験勉強を開始すればいいのかを整理していきましょう。
まずは、初学者の方が独学で学習する場合と学校を利用する場合とで、学習スケジュールがどのようになるのか整理しシミュレーションしてみました。
■独学の場合
| 学習時間/日 | 学習時間/週 | 必要な月数 |
| 5時間 | 35時間 | 5ヶ月半 |
| 4時間 | 28時間 | 6ヶ月半 |
| 3時間 | 21時間 | 9ヶ月 |
| 2時間 | 14時間 | 13ヶ月 |
■学校利用の場合
| 学習時間/日 | 学習時間/週 | 必要な月数 |
| 5時間 | 35時間 | 4ヶ月半 |
| 4時間 | 28時間 | 6ヶ月 |
| 3時間 | 21時間 | 8ヶ月 |
| 2時間 | 14時間 | 11ヶ月半 |
人によって生活スタイルは十人十色ですので一概には言えませんが、在職中の社会人が1日平均4時間以上学習時間を設けるには厳しいものがありますよね。。
ですので、1日平均3時間を目安に見ていただけると現実味があると思います。
1日平均3時間で独学者で約9ヶ月、学校利用者で約8ヶ月かかりますので、試験月の11月から逆算して以下の月から始めるのがいいのではないでしょうか。
- 独学者 → 2月
- 学校利用者 → 3月
ただ、社会人であれば平日に3時間確保するのも正直難しいかもしれませんし、たまには休むことも必要でしょう。
ですので、休日多めに学習したり、たまにはリフレッシュする日を作って心身ともに回復させるなどして調整するとよろしいかと思います。
たまたま仕事で急な残業があったり、ライベートでも予期せぬトラブルで勉強できない日も増えるかもしれませんし、予定通りに学習が捗るとも限りません。余裕をもって上記よりもさらに1か月程度前倒しして勉強を始めるとより予定も組みやすくなると思いますよ。
効率的な勉強時間の使い方


次に効率的な勉強時間の使い方をみていきたいと思います。
正直忙しい日常生活において学習時間を確保するのはそう簡単ではありませんし、特に社会人の方にとっては1時間すら取るのが厳しい方もいるでしょう。
しかし、工夫さえすれば案外勉強時間を捻出できるものです。具体的にどのようにして学習時間を捻出し、かつ効率的に時間を活用するのかについて触れていきましょう。
今回は以下の2つの方法をご紹介します。
- 場所にこだわらない
- 勉強計画表を作る
順番に詳しく解説していきますね。
場所にこだわらない
まずは場所にこだわらないことです。
勉強時間が確保できない人は、自宅の「決まった場所でしか学習しない」または「決まった場所でしか学習する気になれない」といった理由が多いようです。
確かに自宅の慣れた学習デスクが一番集中しやすいのは分かりますが、場所にこだわっていると忙しい日常生活において確保できる学習時間が限られてしまいます。
ですので、こだわりを捨てて細切れで少しでも学習できる環境を作っていきましょう。
1日の生活においておすすめの学習タイミングを以下にまとめてみました。
- 早朝・起床後
- 通勤・通学などの移動中
- 休憩時間・昼休み
- トイレ
- 入浴中
こちらも順番に解説していきますね。
早朝・起床後


1つ目は早朝・起床後です。
朝は通勤・通学前の準備で忙しく、勉強するなんてとても考えにくいかもしれませんが、実は早朝・起床後のタイミングがとても集中しやすい状態となっています。
その理由は、脳内では睡眠中に記憶が整理され、目覚めたときにはリフレッシュされているためです。
このタイミングでは時間が限られているので、無理に新しいことを覚えるのではなく、前日覚えたところや過去問で復習するなどできれば効率がいいでしょう。毎朝10分でも確保できるように努力したいところです。
通勤・通学などの移動中


次に通勤・通学などの移動中です。
職場や学校が近い方は対象外になりますが、通勤・通学などの移動時間を毎日積み上げていくと結構な時間になります。片道1時間なら1日往復2時間費やすわけですからね。この時間を無駄にしてしまうのはかなり勿体ないですし、勉強に活用しない手はないでしょう。
電車やバスなど公共交通機関を利用する方は参考書を精読したり、動画教材の視聴などができますし、自動車を運転する方はオーディオブックやリスニング教材など、耳で聞きながら学習する方法がおすすめです。
公共交通機関を利用する方の場合は周囲の目が気になるかもしれませんが、自分が思っているほど周りは見ていませんので、気にせず頑張りましょう。
片道30分でも学習できれば、通勤・通学時間だけで1日1時間確保できますので、ぜひ試してみてください!
休憩時間・昼休み


休憩時間・昼休みのスキマ時間も有効活用することができます。
休憩時間こそ限られた短い時間ですが、たとえ5分の細切れ時間であっても十分効果が出るでしょう。
時間の使い方としては、朝通勤時に学習したところの続きや、単語カードやスマートフォンアプリを活用した暗記などがおすすめ。
通信講座などの学校利用者であれば、講義動画を倍速で再生し10分以内で1コマ視聴することも可能ですし、意外にできることがあるのでやってみる価値はあるでしょう。
トイレ


トイレも学習するのにおすすめのタイミングになります。
「トイレまで!?」と思うかもしれませんが、トイレは狭い個室空間により安心感と集中力が高まるようです。
問題集などを持ち込むのは衛生的に良くないので、狭い空間を利用して壁やドアなどに覚えておきたい内容や用語を書いた紙を貼るなどすると良いでしょう。
トイレは1日のうち出入りも多いので、繰り返し目にして暗記ができます。
長くても10分程度の滞在になる場所なので、視覚的に記憶しやすいシンプルな内容が適しています。
公共のトイレでは次の方の迷惑になるので、あくまでもご自宅で!
入浴中


最後は入浴中です。
身体を洗い終え湯船に浸かるタイミングは心身ともにリラックスしているため、記憶力や集中力が高まる傾向にあります。
トイレと同様に個室であり静かな空間ですので、勉強する場所として条件は揃っていることになります。
濡れてしまうリスクがありますので、最悪濡れても問題のない要点をまとめたルーズリーフをクリアファイルに入れたり、透明なビニール袋に入れるなど工夫すれば学習は可能です。
ただ、長く浸かりすぎてのぼせてしまうと集中力が低下するだけでなく体調も崩しかねないので、十分注意してくださいね。
通信講座を有効活用するといつでもどこでも学習できる!


上記のように場所にこだわらずに勉強するには通信講座が圧倒的におすすめです。
通信講座ならスマホ1台あれば講義視聴やテキスト閲覧、問題集など様々な勉強ができますので、移動中や家事の合間なんかにも学習を進められます。
当サイトでは、「スマホでの学習に最適な通信講座おすすめ5選」という記事も書いておりますので、ぜひこちらも参考にして下さい。




勉強計画表を作る


次に勉強の計画表を作る事です。
勉強を確実にこなし続けていくには、勉強の計画を立てておくことが重要になります。
今後進めていくべき勉強内容を書き出していくだけで、モチベーションが上がるなど、メンタル面に大きく影響を与える効果があります。
ポイントとしては、作成した計画表をすぐ目に付くところに貼るなどして掲げることです。やるべきことが一目でわかり、かつモチベーション維持にもなりますからね。
エクセルでまとめただけ、手帳に書いただけでは見る前にモチベーションが下がってしまうリスクがあります。
また、計画表を作ることで以下の通り他にもメリットがあります。
- やるべきことが一目でわかる
- 目標に向かって焦らず取り組める
- 勉強する習慣が身につく
- 計画をクリアするごとに達成感を味わえる
- 効率よく学習ができる
行政書士試験に向けての計画表を作成するのは少々面倒で大変な作業になりますが、メリットがたくさんありますので、作ってしまえば役に立つこと間違いなしでしょう。
ただし、あくまでも自分に合った計画を立てる事が大切です。
1日の勉強量が多すぎたり休みなしのハードスケジュールだと、精神的負担が重く挫折の原因になるだけでなく、体調も崩してしまいかねません。
まずはじっくり考えて自分の取り組みやすいペースを把握して計画を立てていきましょう。
まとめ


ここまで、行政書士試験に合格するために必要な勉強時間や勉強開始時期について解説してきました。それぞれおさらいしておきましょう。
- 独学者 → 800~1,000時間程度(2月開始)
- 学校利用者 → 700~800時間程度(3月開始)
数字だけ見ると人によっては意外に少なく感じるかもしれませんが、実際に勉強してみるとかなり長く感じますし、毎日継続し続けるには強い精神力が必要になります。
試験に向けて予定を立て対策しても、テレビや遊びなどの甘い誘惑に負けてしまえば全ての歯車が狂ってしまい台無しになるなんて事がよくありますので、いかにして毎日継続できるかが最も重要になります。「継続は力なり」ってやつです。
本文中にもお伝えした通り、効率よく勉強を継続するには場所にこだわらずにスキマ時間も有効活用するのがおすすめです。そうなると最適な勉強方法は通信講座になります。
当サイトでは「スマホでの学習に最適な通信講座おすすめ5選」という記事も書いておりますので、こちらも参考にしながら通信講座の強みなんかを感じていただければと思います。




行政書士の資格を手に入れることができれば就職や転職に有利で長く活躍が期待できますし、多少無理をしてでも取る価値がある資格だと思いますので、自分に負けず頑張って合格を目指しましょう!