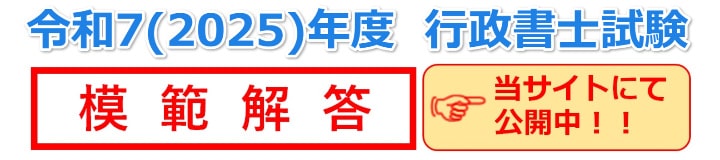- 1年前から学習開始したけど、全科目学習できなかった
- 思うように勉強が捗らなかった
行政書士試験にチャレンジされた方の中には、このような経験をされた方も多いのではないでしょうか。
行政書士に限りませんが、試験に失敗した理由の多くは計画を立てずやみくもに学習をし、効率が悪くなってしまった事が原因です。
「計画を立てるなんて時間がかかるし面倒くさいじゃん」と思うかもしれませんが、進捗状況やその日のやるべき事が容易に把握できますし、試験までのモチベーション維持と安心感も得られますので、計画を立てるのは非常に重要な作業になります。
しかし、ただ計画を立てるだけではあまり効果はありません。しっかりとゴールを見据え、ポイントを押さえながら効果的な計画を立てていく必要があります。
そこでこの記事では、行政書士試験の計画を立てる上で非常に重要なポイントを以下の3つの項目に分けて解説していきます。
- スケジュールは逆算で立てて、学習開始時期を決める
- 月別のスケジュールを3つに分類する
- 試験直前の1か月は、とにかく実戦形式の過去問を繰返し解く!
ぜひ参考にしてください!
【ポイント1】スケジュールは逆算で立てて、学習開始時期を決める


まず、スケジュールはゴールから逆算で立てていくことが大事です。
流れとしては以下の通りです。
- 合格に必要な学習時間を把握する
- 1日の学習時間から開始時期を決定する
順番に詳しく解説していきますね^^
①合格に必要な学習時間を把握する


まず、自分が学習するスタイルならどの程度時間が必要なのかを確認しましょう。
学習スタイルは大きく分類するなら独学と学校利用の2パターン。それぞれ学習スタイルが異なりますので、必然的に学習時間も異なってきます。
目安の総学習時間は以下の通りです。
- 独学者 → 800~1,000時間
- 学校利用者 → 700~800時間
個人差がありますのであくまでも目安となりますが、最低でもこれくらいの時間を念頭に置いておくといいでしょう。
行政書士試験の合格に必要な勉強時間と勉強開始時期の詳細は、以下の記事を参考にしてみてください。


②1日の学習時間から開始時期を決定する


合格に必要な学習時間を導き出したら、次に1日あたりの学習時間から開始時期を決定します。
まずは以下の計算方法で勉強の必要日数を算出しましょう。
合格に必要な学習時間 ÷ 1日に学習できる平均時間
例えば、合格に必要な学習時間が900時間で、1日平均3時間学習することができるなら以下のような答えを導き出すことが出来ます。
例①)
900時間 ÷ 3時間 = 300日(約10ヶ月)
必要日数が分かれば、あとは逆算して勉強開始時期を決めるだけです。試験月は11月なので、上記の例の場合は1月から勉強を開始すると試験に間に合ういうことになります。
ちなみに、計算しシミュレーションすると気付くのですが、1日の学習時間が平均1時間減ってしまうだけで、期間がかなり延びてしまいます。
下記の例では5か月も延びてしまうという結果になります。
例②)
900時間 ÷ 2時間 = 450日(約15ヶ月)
それだけ、1日にどれだけ学習できるかは重要だという事ですので、安易に「3時間くらいできるでしょ」と軽く決めず、自分の現状を洗い出して少々甘めに見積もることをおすすめします。
計画倒れになっては元も子もないですからね。
【ポイント2】月別のスケジュールを3つに分類


自分が1日にどれくらい勉強ができていつ頃から始めるべきか導き出せたら、次は具体的にどのような学習をするのか、およその期間で良いので決めていきましょう。
学習の枠組みを決めてから計画通り実行することで、より効率的に進めていくことができます。
行政書士の学習スケジュールでは、試験前の1か月を除くと、「準備・実行期」「インプット学習期」「アウトプット学習期」の3つの期間に分けるのがポイントになります。
それぞれの目安時間としては以下の通りです。
- 【準備・実行期】 約90時間
- 【インプット学習期】 約540時間
- 【アウトプット学習期】 約180時間
では、以下の条件を例にして順番に見ていきましょう。
例)
開始時期 :1月
1日の平均勉強時間:3時間
準備・実行期


この時期に要する目安勉強時間:約90時間
1月(最初の1ヶ月目)は、準備・実行期として充てます。
何気なく学習を開始するのではなく、まずは全体的にどんな科目があり何を学習すべきなのか、どのような流れで取り組んでいくべきなのかを把握しましょう。
何も把握しないままいきなり学習を開始してしまうと、全体が見えず効率が悪くなったり期間内に全科目学習しきれないなど、よくありがちなミスを起こしやすくなります。



学習開始時期が決まっても、やるべき事が分からなかったら元も子もありません
大まかに理解したら、実際に勉強に移っていきます。勉強に移るといっても、ここではあくまでサラッと流し読みでテキストを1周する程度でOKです。
特に学習初心者の方はいざ学習開始してみると内容が難しく専門用語も多いので、四苦八苦するかもしれません。
それでもやらなければゴールに辿り着けないので、多少前無理をしてでも予定時間通り学習をして、少しずつ慣らしていきましょう。
受験経験者は、前回チャレンジした試験の復習を肩慣らしで感覚を思い出しながら勉強し、モチベーションを上げていく準備期間としていきましょう。
また、過去の試験で不足していた個所を、重点的に補えるようなプランを練っていくべきですね。
- 学習範囲全体を把握する
- 専門用語が多く苦戦するかもしれないが、最初はとにかく計画通りに
- 試験経験者は前回の復習に充てて肩慣らしを
インプット学習期


この時期に要する目安勉強時間:約540時間
2月から7月末までの6ヶ月はインプット学習期間です。この期間で基礎事項の学習をしっかり行い、どんどん知識を向上させていきましょう。
学習方法としては、独学者は過去問やテキストをこなし、学校利用者であれば各科目の講義を順次受講していき、基礎の内容に数多く触れていくことです。
行政書士試験では合格ラインが6割以上で、実は基礎内容をしっかり理解できれば合格ラインの点数を取れるように設計されているのです。
満点を取れなくても合格は合格ですので、まずは徹底的に基礎を理解するように進めていきましょう。
※足切り制度には注意!※
行政書士試験には、全体得点以外にも2つの合格基準点があります。
全体得点が60%に達しても、下記がクリアできなければ不合格になるのでご注意ください。
・行政書士の業務に関し必要な法令等 → 満点の50%以上
・行政書士の業務に関する一般知識等 → 満点の40%以上
進めていくと分からない内容が出てきて壁にぶつかってしまう事もありますが、その場合は一旦保留にして先に進むことをおすすめします。
範囲が広く悩んでいる時間が勿体ないので、基本的にはスケジュール通り進めることを心がけて下さい。
分からないところは過去問を反復しているうちに理解できることもありますし、それでも理解できない場合は、後で学習する時間を別に設けるなどできますからね。
6ヶ月間は一見長く感じるかもしれませんが、いざチャレンジするとあっという間です。この期間内に基礎事項を徹底して理解することができれば、土台が完成し自信につながりますので、頑張って乗り切りましょう。
- 過去問やテキストをフル活用して基礎内容を徹底的に覚える
- 理解できない部分はとりあえず保留で先に進むことを意識する
アウトプット学習期


この時期に要する目安勉強時間:約180時間
8月から9月までの2か月間はアウトプット期間になります。
ここではインプット期間に養った知識を基に答案教材で学習をを行ったり、模擬試験にチャレンジしていきます。
まず模擬試験では自分の現段階の実力を把握する事が可能。これによりどこを重点的に強化すべきなのかを分析できるようになります。



得意分野を伸ばしていくよりは、点数を稼げていない苦手分野を潰すために基礎を徹底的に学習し直す方が得点獲得効率が高いので、どんどんやり込んで苦手分野を少なくしていきましょう!
また、この期間に事例問題(短答記述)に対応する力もつけていく必要があります。行政書士試験では例年3題は必ず出題され、点数は60点分(20×3問)にもなりますので無視できません。
この期間で一気に合格ラインに近づけていきましょう。
- 模擬試験データを利用して弱点の分析・対策をする
- 苦手箇所を重点的に学習して足切りにかからないようにする
- 事例問題(短答記述)は60点分(20×3問)と大きいので抜け目なく
【ポイント3】試験直前の1か月は、とにかく実戦形式の過去問を繰返し解く!


試験直前の10月(ラスト1ヶ月)は最終確認を行う時期です。
ここでは本番までをどう過ごすかといった最終調整がカギになってきます。
やるべきことは、記憶を定着させるために実戦形式の過去問を繰返し解くことです。脳だけでなく視覚的にも残りますので、とにかく繰り返しやっていくだけで大きな効果が得られます。
あと、試験本番を意識して問題を解いていく練習をするのも効果があります。行政書士の試験は60問を180分で解答しなければならず、単純計算で1問にかけられる時間は約3分となっております。
「3分もあるんだったら余裕そう」と思うかもしれませんが、実際は時間が足りなくなることが多くあります。そうならないためにも、ある程度練習して臨み、焦らず冷静に問題を解いていけるようにしましょう。
試験直前期の注意点


この期間に注意していただきたいのは、知らない論点を見つけて不安になり、直前になって焦って学習してしまわないことです。
この場合は思い切ってスルーしてしまいましょう。(ただし、足切りにかからない程度が条件)
明らかに理解と暗記するまでに時間が足りませんし、その時間を使うのであれば、これまで勉強してきた基礎知識を完璧にした方がよっぽど得点を高くできる可能性がありますからね。
これまでに覚えてきた内容を忘れないことを念頭に置いて、ラストを乗り切りましょう!
- 実戦形式で過去問や模擬試験を何度も解き直す
- 本番と同じ条件で問題を解く
- 知らない論点を見つけてしまったら思い切って諦める
まとめ


ここまで学習計画を立てる上での3つのポイントについて解説してきました。
計画をきっちり立てるのは正直手間がかかりますし大変ですが、ゴールまでの道のりを決めさえすれば、段階的に進めていけるので間違いなく近道になるでしょう。
計画を立てずに失敗した例をよく聞きますし、計画を立てたものの間違った計画を立ててしまい、修正できないまま期間が過ぎてしまったといったケースもよくあります。そうならないためにも、上記の3つのポイントをしっかり意識してより効果的な計画を立ててください。
なお、当サイトでおすすめしている通信講座のフォーサイトでは、生活スタイルを入力するだけで自動的に学習可能時間を算出し、最適な学習スケジュールを作成してくれるツールが用意されています。


無料資料請求をすればこういった機能を実際に使用することもできますので、計画を立てるのが苦手な方はぜひ一度試してみて下さい^^


\今なら10,000円OFFクーポン付き!/