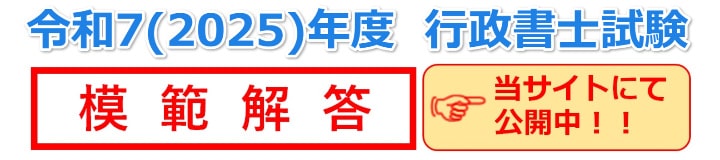弁護士/司法書士/行政書士はどれも共通して難しそうという認識はあるけど、どう違うのかイマイチ分からないという方も多いのではないでしょうか。
弁護士はドラマやアニメなどで多く取り上げられているのでまだイメージがつきやすいですが、司法書士と行政書士とでは特に違いが分かりにくいと思います。
弁護士/司法書士/行政書士の業務には重なる部分もありますが、それぞれに独占業務もあり、得意分野が異なります。
この記事では、各資格の仕事内容の違いや給与・年収、難易度の差などについても詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士/司法書士/行政書士それぞれの特徴を解説
まずは弁護士/司法書士/行政書士それぞれの特徴を見ていきましょう。
主な業務内容や取り扱い不可な案件などもまとめてみました。
弁護士とは


弁護士は法律業務において金額や種類を問わず、すべての事件の相談を受け、依頼人に代わって交渉や裁判をすることができます。つまり、法律業務に関わる案件に対してはオールマイティに対応できるのです。
弁護士は主に、法律の専門家の立場から適切な対処方法及び解決策のアドバイスを行ったり、紛争を防止するという予防的観点からも助言を行うことが基本的な役割となっております。
このように、社会生活について様々なアドバイスを行っているため、「社会生活上の医者」とも呼ばれています。
弁護士の主な業務内容は以下の通りです。
- 依頼者からの法律相談で交渉・訴訟を行う
- 法律に関する書面を作成する
- 裁判手続を依頼者の代わりに行う(代理)
- 被疑者・被告人の権利を擁護する弁護人となる
法律業務に関わる案件に対してはオールマイティに対応できますので、弁護士の一般的なイメージである依頼人に代わって交渉や裁判をすること以外にも、法律に関する書面の作成や手続きを代理で行うなどの業務もあります。
少しでも法律が関係することであれば、弁護士の力を借りて解決の糸口を探ることができますので、人々から大きな信頼を得やすい職業といえるでしょう。
司法書士とは


次に司法書士です。司法書士の一番の特徴としては、不動産登記や商業登記等、登記という制度に関する専門家であることです。
主な業務は下記のとおりです。
- 依頼者からの法律相談で交渉・訴訟を行う(140万円以下)
- 不動産登記、会社の登記・供託の手続き代理で行う
- 簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理を行う
- 法律相談、企業に関する法律事務を行う企業法務
- 成年後見事務、多重債務者の救済、消費者教育
例えば一軒家を購入した際、銀行へおもむき「決済」というとても重要な手続を行うのですが、その際必要書類の確認をおこなったり、契約した家主の代理人として登記手続を担うのが司法書士です。
一軒家を建てる人からすれば、人生において一世一代の大きな買い物に携わる仕事ですので、かなり重要な役割ですよね。
また、司法書士でも弁護士のように事件の相談を受けたり、依頼人に代わって交渉や裁判をすることも可能です。
弁護士と違うところは、案件によっては取り扱いできない制限がある点です。
- 離婚・相続などの家事事件(相談、書類作成までは可能)
- 140万円以上の金額の事件
家事事件においては、弁護士のように依頼人に代わって交渉や裁判を行うことはできません。
できたとしても相談を受けて裁判所に提出する書類を作成することまでとなっております。
また、140万円以上の案件に関してはそもそも取り扱い不可となります。
行政書士とは


最後に行政書士の特徴を見ていきましょう。一番の特徴としては、行政書士にしかできない独占業務があるというところです。
その内容は官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出手続きを行う業務になります。
その他、行政書士の主な業務内容は以下になります。
- 依頼された書類作成について相談
- 国や地方公共団体など、官公署に提出する書類作成
- 事実証明に関する書類作成(実地調査に基づく図面類を含む)
- 権利義務に関する書類作成
- 許認可申請の代理を行う
例えば飲食店の開業や古物商許可、建設業許可など、世の中ではありとあらゆる許認が必要ですが、これらを依頼人に代わって必要書類を作成し、手続きの代理を行います。
権利を証明する契約書や内容証明の書類を当事者の言い分どおりに作成することもできます。
また、行政書士にも対応できない取り扱い制限があります。
- 離婚・相続・交通事故などの一般的なトラブルの相談
- 依頼人に代わって交渉や裁判をすること
トラブル相談や依頼人に代わって交渉や裁判を行うことはできません。
これらの案件は弁護士か司法書士に依頼することになり、行政書士が書類作成のサポートで携わることは可能です。
各項目ごとに見る弁護士/司法書士/行政書士の違い


上記でそれぞれの資格の特徴を解説してきました。
ここからは、各項目ごとに3資格の違いを見ていきましょう。
以下の4つの観点で比較してみたいと思います。
- 試験内容
- 難易度
- 業務範囲
- 給与・年収
順番に解説していきますね。
試験内容の違い
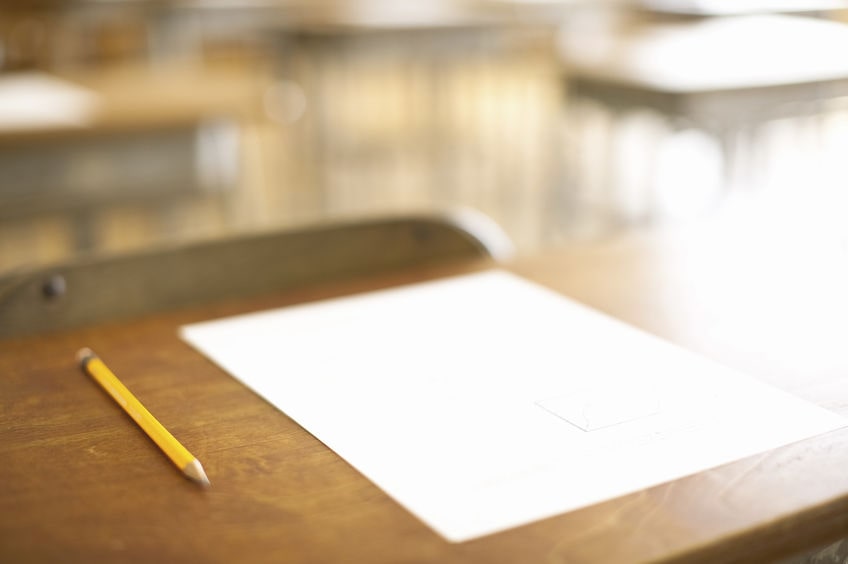
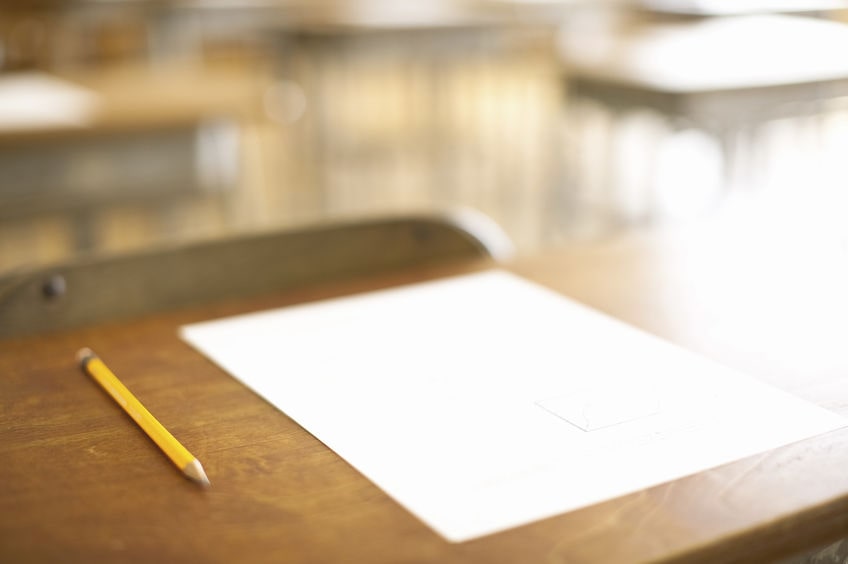
まずはじめに試験内容の違いについて見ていきましょう。
どれも法律系の試験になりますので、そう簡単に受かることのできない難関資格となっております。
しかし、同じ法律系の分野であれど、試験内容や出題される科目、傾向において特徴があります。
一覧にまとめてみましたのでご確認ください。
| 弁護士(司法試験) | 司法書士 | 行政書士 | |
| 試験回数 | 1年に1回 | 1年に1回 | 1年に1回 |
| 受験資格 | 法科大学院修了者もしくは予備試験合格者 | 特になし | 特になし |
| 試験方法 | 短答式と論文式。4日間にわたり全科目の短答・論文式試験が行われる | 筆記と口述試験。口述は筆記試験合格者のみが受験 筆記試験には、択一問題と記述式問題がある (※解答の分量はA3見開きが2枚/1問、計2問) | 筆記試験のみで、口述や面接はなし 筆記試験には、択一問題と記述式問題がある (※解答の分量は40字程度が3問) |
| 科目 | 憲法・民法・刑法・行政法・商法/会社法・民事訴訟法・刑事訴訟法・選択科目 | 憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・司法書士法・供託法・不動産登記法・商業登記法 | 基礎法学・憲法・行政法・民法・商法/会社法・一般知識 |
このように表にまとめてみると、3つそれぞれが違うのがわかりますね。
行政書士は試験方法が筆記試験のみの1種類に対して、弁護士と司法書士は筆記プラスαありますので、それに合わせた試験対策が必要。
また、弁護士は4日間にわたり試験が行われるので、非常に大掛かりな試験になります。
科目では、基礎的な科目は被っているところもありますが、司法書士であれば不動産登記法・商業登記法があるなど、やはりそれぞれの専門的な業務に必要な科目が盛り込まれています。
難易度の違い


続いては難易度を見ていきましょう。
まずは、合格に必要なおおよその学習時間と、それぞれの過去5回分の合格率を表にまとめてみました。
■学習時間
| 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
| 学習時間 | 6,000時間 | 3,000時間 | 800時間 |
■過去5回分合格率一覧
| 実施年 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 |
| 2023年 | 45.3% | 5.2% | 14.0% |
| 2022年 | 45.5% | 5.2% | 12.1% |
| 2021年 | 41.5% | 5.1% | 11.2% |
| 2020年 | 39.2% | 5.2% | 10.7% |
| 2019年 | 33.6% | 4.4% | 11.5% |
| 平均 | 41.0% | 5.0% | 11.9% |
これらを比較したところ、「弁護士って他の2資格より合格率高いじゃん!」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
そもそも弁護士試験を受けるには受験資格が必要で誰でも受験できるわけではないのです。受験資格のある法科大学院修了者もしくは予備試験合格者が受けた上での数字ですので、いかに狭き門かが分かるでしょう。
学習時間においても弁護士が圧倒的に費やす時間が多いとされていますので、相当難易度が高いのが伺えます。
行政書士は他の2資格よりも学習時間が短く比較的簡単に受かりそうに見えますが、それでも法律系の難関資格ですし一筋縄ではいきません。
なお、学習時間はあくまでも目安であり、個人差がありますのでご容赦ください。
業務範囲の違い


次にそれぞれの業務範囲を見ていきましょう。
こちらも分かりやすいように一覧にまとめてみました。
| 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
| 140万円以下の法律相談・交渉・訴訟 | 認定司法書士のみ | ||
| 140万円以上の法律相談・交渉・訴訟 | |||
| 遺言書の作成 | |||
| 不動産の名義変更 | |||
| 後見人の申し立て | 書類作成のみ可 | ||
| 遺産分割調停・裁判の代理人 | 書類作成のみ可 | 書類作成のみ可 | |
| 遺産分割協議の代理人 | |||
| 遺産分割争いに関する法律相談 | |||
| 相続に関する管理や処分等の手続 | 書類作成のみ可 | ||
| 遺言書執行に関する手続 | 書類作成のみ可 | ||
| 離婚調停・裁判の代理人 | |||
| 離婚協議の代理人 | |||
| 離婚争いに関する法律相談 | |||
| 離婚協議書の作成 |
このように表で比較してみると、弁護士のオールマイティさがよく分かりますよね。
対照的に行政書士はかなり業務範囲に制限がかかっています。
対応できる業務が被ってるところもありますが、例えば不動産関連の案件では司法書士が専門であるように、弁護士でも対応ができるけど、司法書士にお願いした方がいい場合もあります。
給与・年収の違い


最後に給与と年収を見ていきましょう。
まずは初任給と年収の平均を表にまとめてみました。
■初任給と年収の平均
| 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
| 初任給 | 568万円/年 | 21万円/月 | 21万円/月 |
| 年収 | 2,558万円 | 1,121万円 | 551万円 |
参照:法務省「法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)」、日弁連「近年の弁護士の活動実態について」、求人ボックス「司法書士の仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」、厚労省「司法書士 – 職業詳細 | job tag」、求人ボックス「行政書士の仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」、厚労省「行政書士 – 職業詳細 | job tag」
初任給においては、弁護士が最難関資格とされているだけあって圧倒的に高い金額となっております。(※ただし、月給データがなかったので年収表示です)
大卒の平均初任給は約20万円ですから、その他2資格においては大卒平均初任給より若干高いくらいです。ただ、これらの職業は独立開業する方が多い仕事になりますので、あくまでも参考程度で宜しいかと思います。
独立開業しなくても安定して高額収入を得られるのは、間違いなく弁護士です。
また、平均年収は資格取得の難易度が高いほど収入も上がる傾向がある事が表で分かります。
ダブルライセンスのメリットと組み合わせの相性について


ここまでの内容を読んで、これらの資格を組み合わせたらどうなるのかと気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここからは、弁護士/司法書士/行政書士のそれぞれの組み合わせでダブルライセンスを目指す場合の相性やメリットについて書いていきたいと思います。
弁護士がダブルライセンスする場合
まずは弁護士です。弁護士は前述したとおり法律系の最難関資格であり、かつ法律関係においてはオールマイティに対応が可能なので、弁護士の資格を先に持っていれば他の2つの資格を持っていてもさほどメリットはありません。
しかし、専門知識を磨き知識向上になる分には損をすることはないです。知識のブラッシュアップという意味では勉強することは悪くないですね。
行政書士と司法書士のダブルライセンス
続いて、行政書士と司法書士の組み合わせでダブルライセンスを取得する場合を見てみましょう。職域を広げやすい組み合わせとして、実際に多くの取得者がいらっしゃいます。
行政書士と司法書士は、共通して書類作成や申請手続きを代行することが仕事ですが、行政書士が官公署での手続きを手掛けるのに対し、司法書士は法務局や裁判所での手続きを手掛けるという違いがあります。
つまり、両方を組み合わせる事でどちらもこなすことができるので仕事の幅が広がりますし、言わば「法的書類のプロ」として活躍することができるでしょう。
行政書士と司法書士から弁護士とダブルライセンスの場合
弁護士の資格を持っている方が他の2資格を取得する場合はあまりメリットがないとお伝えしましたが、逆に行政書士、司法書士から弁護士を取得してダブルライセンスとする方は多いです。
ダブルライセンスというよりは、行政書士や司法書士からステップアップで弁護士資格を取得するといった感じでしょうか。そのため、行政書士や司法書士で培った経験を活かし弁護士として働くという事になります。
行政書士、司法書士から弁護士にステップアップできれば、業務範囲の制限といった壁が無くなるわけですからメリットが大きいでしょう。
まとめ


ここまで弁護士/司法書士/行政書士の違いについて解説をしてきました。
まず、これらは同じ法律系の業種になりますが、それぞれの業務内容や特徴など違いが多くあるという事はおさえておきましょう。
依頼する側からすれば「オールマイティな弁護士にすべて依頼すればいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、不動産の登記や官公庁へ提出する申請書類の作成業務などは、司法書士や行政書士の方にお任せしたほうがスムーズにできることもあります。金額面でも司法書士や行政書士の方が安い場合が多いですからね。
そのため、弁護士も司法書士や行政書士とタッグを組んで、それぞれの専門性を活かしながら仕事をしていくことが多いです。
これから法律系の資格取得を目指している方は、自分の興味や得意とする分野にあった仕事をする方が間違いなく力を発揮できますので、各業務の違いを把握した上でチャレンジをする事をおすすめします!