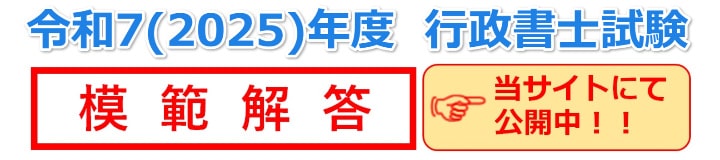「行政書士の資格を取ろうか迷っているけど、どうしよう…」
「この資格って役に立つのかな?取る意味あるのかな?」
行政書士の勉強を始めようか考え中の方で、このように悩んでおられる方も多いのではないでしょうか?
行政書士は基本的に企業などを相手に仕事をしているので、日常生活で行政書士の仕事に触れることもほぼなく、他の職種に比べてなかなか想像がしづらいですよね。
そこでこの記事では、行政書士資格を持つメリットや魅力を7つピックアップしてみました!
- 行政書士資格が必要な仕事ができる
- 試験難易度は法律系資格の中では易しい部類
- 法務事務所で使用人行政書士として働くことができる
- 行政書士として独立開業して働ける
- 就職・転職に有利になる
- ダブルライセンスで仕事の幅が広がる
- 将来性がある
それぞれ詳しく解説していきますので、行政書士資格を取ろうか迷っておられる方はぜひ参考にして下さい!
行政書士資格が必要な仕事ができる


まず、当たり前ですが資格を取り行政書士会へ登録をすれば行政書士になれます。
ということは、必然的に行政書士が行える仕事ができるようになるわけです。
行政書士の主な仕事は、許認可に関する書類を作成、申請を代行したりすることで、その中には行政書士のみが行える独占業務が存在します。
行政書士の独占業務は主に以下の3つです。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する作成
行政書士が取り扱える書類の範囲はかなり広く1万種類以上あり、行政機関等に提出するものなどは資格がないと取り扱えないものがたくさんある上に、これらは法律で定められているので他士業では同じように取り扱うことができません。
ただ、同じような業務内容でも他士業との間でできる範囲、できない範囲が存在するので注意が必要です。例えば以下のようなパターンが挙げられます。
例)
会社設立の手続き時の定款の作成、公証人役場での認証手続きは行政書士、司法書士ともに扱えるが、設立後の登記が必要になる部分に関しては法務局が絡むので司法書士のみ取り扱いが可能。一方、役所を通す各種手続き、自動車、外国人に関連する手続きなど、司法が絡まないものは司法書士が行うことができない業務です。
行政書士になった際は、手続き等で他士業の独占業務に触れないよう気をつけながら業務を進める必要がある点は押さえておきましょう。
試験難易度は法律系資格の中では易しい部類


行政書士資格はれっきとした国家資格であり、いわゆる法律系の資格ですが、他の法律系資格に比べると難易度は比較的易しめです。
過去5年の他法律系資格の合格率を比較してみましょう。ここでは社労士と司法書士を取り上げてみました。
■過去5回分合格率一覧
| 実施年 | 社労士 | 司法書士 | 行政書士 |
| 2023年 | 6.4% | 5.2% | 14.0% |
| 2022年 | 5.3% | 5.2% | 12.1% |
| 2021年 | 7.9% | 5.1% | 11.2% |
| 2020年 | 6.4% | 5.2% | 10.7% |
| 2019年 | 6.6% | 4.4% | 11.5% |
| 平均 | 6.5% | 5.0% | 11.9% |
上記の表の通り、ここ5年の行政書士試験の合格率は10%以上をキープしており、他2資格の約2~3倍の合格率となっていることからも、試験難易度は易しめであることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
もちろん、それでも大体10人に1人しか受からないような試験なので心して勉強する必要があることは言うまでもありません。
なお、行政書士試験の合格ラインは以下の通りとなっております。
- 全体得点 300点中180点(60%以上)
- 法令科目 244点中122点以上
- 一般知識科目 56点中24点以上
このように、各科目である程度合格ラインも分かっているので、合格を目指す場合は苦手科目をなくすことも大切になってきます。
法務事務所で使用人行政書士として働くことができる


行政書士資格を取得することで、行政書士事務所などの法務事務所に所属し、「使用人行政書士」 として働くことができるのも魅力のひとつです。
雇用されて働くので、スピードを求められたり、求人があまり多くないため就職が難しいなどの難点はありますが、開業行政書士のように経営状況などを心配しなればならないというデメリットはありません。
また、開業を目指す方は事務所で働きながら経営のノウハウを学ぶことができるのも嬉しいポイント。多くの場合、最初は電話・お客様応対などの業務をこなし、その後は書類準備や作成など行政書士の業務に深く関わることができます。
行政書士事務所が取り扱う業務の中には在留資格、相続、帰化申請など様々な業務がありますが事務所によって強みが違いますので、自分が取り扱ってみたい分野に強い事務所を探してみましょう。
行政書士として独立開業して働ける


行政書士として独立開業できるのも魅力のひとつですね。
PC、電話、FAX、ホームページがあれば自宅でも開業することができ、相場はありますが報酬なども自分で決めることが可能です。
当然、経営・営業能力がないと仕事を取ることや稼ぐことは難しいですし、責任がすべて自分にあるという厳しさもありますので覚悟も必要になってきます。
平均年収については約600万円程度といわれていますが、こちらはかなり個人差があり、200万円ほどの行政書士もいれば年収1,000万円を超える行政書士も存在しています。
つまり、自分がどれだけ頑張るかによって見返り(報酬)も変わってくるということですね。年収も仕事内容も自分次第、やりがいのある働き方であることは間違いないでしょう。
就職・転職に有利になる


行政書士資格を取得すれば就職・転職にも有利になります。
例えば、法的知識自体が必要な仕事としてパラリーガルが挙げられます。
パラリーガルとは)
弁護士の指示のもと法律事務業務を補佐するのが主な仕事。法律の論文や判例調査など各種資料を集める仕事などもあります。
パラリーガルになるのに必要な資格というのはありませんが、法令、判例に触れる仕事の為、行政書士の資格があるのは有利でしょう。
また、企業の法務部は実務経験必須であったり大手国際企業で英語力にコミュニケーション能力が同時に求められてしまうところも多くありますが、ベンチャー企業や、地頭の良さ・やる気などを重視している企業であれば行政書士資格を採用に活かせると思います。
他にも、建設業では建設業許可申請の知識が武器になることもありますし、その他士業の事務所においても活躍の場があるでしょう。
このように、行政書士資格が企業のニーズに合えば採用の武器になることもあり得るのです。
もちろん、行政書士や法的知識が必要ない企業であっても、目標に向かって努力できる精神的な強さや、記憶力などもアピールできるので、就職・転職において有利であることは間違いありません。
【注意】一般企業内で行政書士として働くことはNG!


ここで1点注意しておきたいのが、一般企業内で行政書士として雇われ働くことはできないと決まっている点です。
行政書士に対して兼業を禁止する法律や規則はありませんが、各都道府県の行政書士会の会則で、行政書士または行政書士法人以外の個人や企業に行政書士として雇われることは禁止となっています。
行政書士には依頼に応ずる義務と守秘義務があり、会社で働いている場合「依頼に応ずる義務」が果たせないためです。
また、働いている中で守秘義務を守れない可能性もあるため、企業内行政書士は禁止されていますが、会社から独立した一事業者として依頼を受け、給料とは別の報酬を受け取ることは可能となっています。
会社の就業規則をしっかりと確認しなければなりませんが、こういった形で行政書士として依頼を受けることもあります。
ダブルライセンスで仕事の幅が広がる


行政書士資格とダブルライセンスで他の資格を持つことで、仕事の幅を広げることも可能です。
様々な資格において行政書士とのダブルライセンスは活かせますが、ここでは司法書士と社労士を例に挙げて解説したいと思います。
行政書士と司法書士のダブルライセンス


司法書士は主に不動産に関する登記・法人の登記などを取り扱う士業。
司法書士にも独占業務があり、裁判所や検察庁に提出する書類の作成などが挙げられます。
行政書士も公的機関に提出する書類の作成を主な業務としてますので、割と近しい業務がメインになるということになりますね。
で、行政書士とのダブルライセンスの相性が良い例をひとつ挙げておきましょう。
会社の設立や土地を含んだ相続においては、行政書士と司法書士が行う手続きが微妙に異なりますが、行政書士と司法書士、この2つのライセンスを持つことで、本来行政書士だけではできない会社設立業務や土地相続問題が扱えるようになります。つまり、一方の資格だけでは完結できない仕事が、もうひとつの資格を持つことで一人で完結できるということですね。
なお、試験科目においては憲法、民法、会社法、商法という重複する部分もあるため、行政書士から司法書士を目指す場合は多少知識を持った状態で勉強をスタートできるという強みもあります。
行政書士と社労士のダブルライセンス


社労士は、年金・健康・社会保険の手続きや、就労規則の作成などの相談を行う国家資格です。
行政書士は会社を設立する際の手続きに活かせますし、社労士は会社設立後に社会保険の加入手続きや雇用保険に関する仕事、就業規則の制定のアドバイスなどを行えるので、行政書士と社労士双方の資格を活かすことができます。
こちらも上記の司法書士同様に、お互いの足りない部分を補い合える相性の良い資格と言えるでしょう。
将来性がある


行政書士は将来性もあります。近年はAIの発達においてどんどん仕事がなくなっていくと言われておりますが、行政書士にはその資格がないとできない独占業務が存在するため、AIに取って代わられる心配はありません。
以下の業務は、行政書士法19条で「行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」と規定されています。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する作成
これらの業務を資格を持たない方がしてしまうと法律に触れ、罰則されてしまいます。
しかも、新たな法律が制定・改訂される度に行政書士が取り扱える書類が増えるので仕事が無くなることは現状考えづらいです。
なお、当サイトの別記事で行政書士のことをより詳しく解説しておりますので、こちらも宜しければ参考にして下さい。


まとめ


ここまで、行政書士資格のメリットや魅力を7つピックアップして解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
最後に、今回ご紹介したメリット・魅力をもう一度整理しておきましょう。
- 行政書士資格が必要な仕事ができる
- 試験難易度は法律系資格の中では易しい部類
- 法務事務所で使用人行政書士として働くことができる
- 行政書士として独立開業して働ける
- 就職・転職に有利になる
- ダブルライセンスで仕事の幅が広がる
- 将来性がある
上記の通り、行政書士資格を取得することで得られるメリットはたくさんあります。
その他にも、行政書士が取り扱える書類の範囲はかなり広く、1万種類以上あるとも言われています。
飲食業許可、医薬品販売行許可などの営業許可系から、外国人のビザ・帰化申請などの外国人サポートに関する書類、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、使用賃借、請負)などの権利義務に関する書類まで、この作成書類の守備範囲の広さも行政書士の魅力の一つです。
「行政書士ってあまり仕事ないよ」とか「行政書士はメリット少ない」という声も世間ではチラホラあるようですが、私自身は非常に魅力たっぷりな資格だと思っております。
この記事を読んで、行政書士の魅力が伝わったのであれば幸いです!ご精読ありがとうございました。