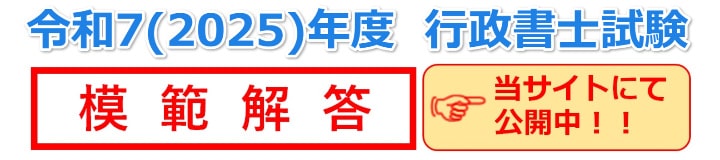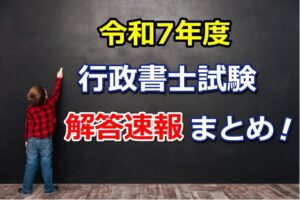行政書士の試験は年に一度しか行われませんので、申し込みのタイミングや手続きなどを間違えてしまうと次の年まで受験できなくなってしまいます。そんなことは避けたいですよね。
申し込みする段階では合格する自信を持っていたい、という方はその期間に合わせて勉強時間を逆算し、計画的に準備を進める必要があります。
落ち着いて試験を受けられるよう、ここでは申込方法や試験日程、その他試験概要などを確認していきましょう!
受験資格
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍など一切関係なく誰でも受験可能です。
受験料


受験料は10,400円です。
- その他払い込みに要する手数料は受験申込者の負担になります
- 地震や台風などの天災、何らかの理由で試験を実施しなかった場合を除き、一度払った受験料が返還されることはありません
申込方法
行政書士試験の申込方法としては以下の通り2つあります。
- インターネットによる申し込み
- 郵送による申し込み
順番に詳しく解説していきますね。
①インターネットによる申し込み


インターネットによる申込期間は例年7月下旬から8月下旬の約1ヶ月間 です。
時間を少しでも過ぎると、たとえ入力中であっても申し込みできませんので注意が必要です。
また、スマホや携帯電話からの申し込みは不具合が起こるため推奨されておらず、登録完了メール受信用のパソコンのメールアドレス、顔写真のカラーデータも必要になります。
- 申込条件に同意し、受験願書・顔写真画像を登録
- クレジット又はコンビニで受験手数料を払い込み
- 登録完了メールを確認、届けば完了
- 3ヶ月以内で受験者本人のみを撮影したカラー写真
- 無帽、無背景、正面上半身の鮮明な写真で、顔がよくわかるもの
- 顔の大きさが全体の4分の3程度あるもの
- 画像データの大きさ縦:横が4:3
- データ形式はJPEG形式
- 試験中めがねを使用する方は、そのめがねを着用した状態の写真
- 集合写真やスナップ写真など、受験写真として不適切なもの、本人確認が困難な写真は不可
なお、行政書士試験研究センターホームページにて、インターネット申し込みに関してよくある質問FAQも記載されておりますので、こちらも参考にしてください。
インターネット申込みについてのFAQ|行政書士試験研究センター
②郵送による申し込み


郵送による申込期間も例年7月下旬から8月下旬の約1ヶ月間ですが、郵送の場合は受験願書・試験案内を受け取る必要があります。
受験願書・試験案内の配布期間は、 行政書士試験研究センターホームページより毎年7月の第2週より案内がありますのでチェックしておいて下さい。
受取方法は、行政書士試験センターに郵便で請求して郵送してもらうか、窓口で受け取るかの2つです。どちらも期間、日程が異なるため間違えないようにしましょう。
願書を請求して郵送してもらう場合、同センターのホームページで指定された期間に請求します。
住所・氏名記載の返信用封筒(角形2号=A4サイズの願書が折らずに入る封筒)に郵送切手140円分を貼付し、下記の宛先まで郵便で請求してください。
〒252‐0299
日本郵便株式会社 相模原郵便局留
一般財団法人行政書士試験研究センター試験課
不備がなければ、順次発送されます。
期間内に郵便局の窓口で受験料を支払い、受領書(振替払込受付証明書)と顔写真を願書に貼付すれば完成です。
- 受験願書に必要事項を記入、顔写真を貼り付け
- 受験手数料を専用の振替払込用紙により郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で払込み(手数料は受験者負担)
- 受験願書に振替払込受付証明書(お客様用)を貼り付け、受付期間内に必ず郵便局の窓口で「簡易書留郵便」扱いの手続きを行い郵送
- 3ヶ月以内で受験者本人のみを撮影したもの
- 正面上半身の縦4㎝、横3㎝のカラー写真
- 顔の大きさは約2.5㎝~3㎝
- 無背景(白、水色、グレーなどの無地背景)のもの
- 試験中めがねを使用する方は、そのめがねを着用した状態の写真
- 集合写真やスナップ写真など、受験写真として不適切なもの、本人確認が困難な写真は不可
- 試験案内が入っていた封筒を利用して下さい
- 受験願書はポストに投函してはいけません
- ATMでの支払いは禁止です
- 以下のような写真は受付できません
・指定の寸法を満たしていない
・ピントが合っていない
・画像処理している(縦長、横長など)
・目を閉じている、正面を向いていない
・眼鏡のレンズに光が反射している
また、ATMでの支払いは禁止という点は注意が必要です。窓口支払いでないと「振替払込受付証明書」がもらえませんし、こちらが貼られていない願書は受け付けてもらえませんので間違えないように注意しておきましょう。
申し込み完了後
申し込みが無事完了すれば、10月下旬に受験票が発送されます。この受験票には受験番号や試験会場などが記載されています。
試験当日は必ず持参し、合格発表も受験番号で公表されるので、それまで大切に保管してください。
試験日/試験会場/持ち物/注意事項・禁止事項 など
試験日


試験は1年に一度となっており、 毎年11月第2日曜日が試験日となっております。
試験は13時~16時で行われ、入室は11時50分から始まり、12時20分までに試験室に入り席に着く必要があります。
12時30分からは受験上の注意事項の説明があります。
試験会場
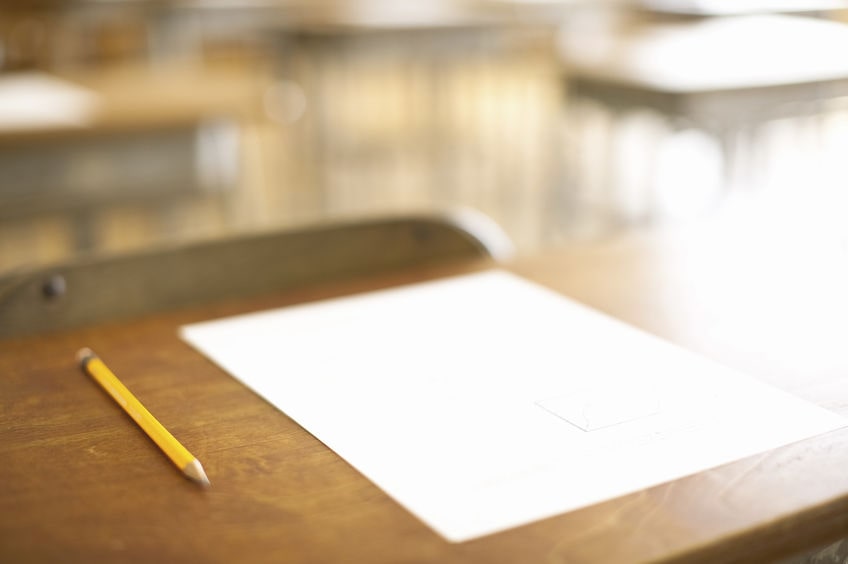
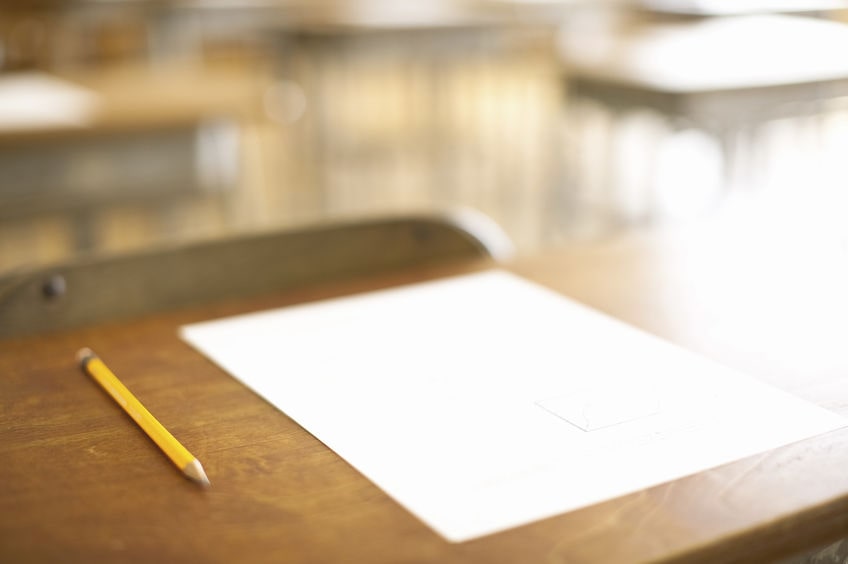
試験会場は願書提出時に希望する試験会場を選択し、原則として先着順に受け付けられます。
受験票に決定された試験会場が記載されている ので、必ず確認しましょう。
以下、令和6年度の試験会場を参考までに載せておきます。
令和6年度 行政書士試験会場
| 都道府県 | 試験会場 |
| 北海道 | 北海学園大学 豊平キャンパス 道北経済センター |
| 青森県 | 青森中央学院大学 |
| 岩手県 | いわて県民情報交流センター(アイーナ) |
| 宮城県 | 東北学院大学 五橋キャンパス |
| 秋田県 | ノースアジア大学 |
| 山形県 | 東北芸術工科大学 |
| 福島県 | 日本大学工学部 |
| 茨城県 | 駿優教育会館 |
| 栃木県 | 宇都宮大学 峰キャンパス |
| 群馬県 | 高崎経済大学 |
| 埼玉県 | 獨協大学 |
| 千葉県 | 日本大学理工学部 船橋キャンパス |
| 東京都 | 日本大学理工学部 駿河台キャンパス 目白大学 新宿キャンパス 東京都立産業貿易センター台東館 TOCビル 明治大学 和泉キャンパス 立教大学 池袋キャンパス 武蔵大学 江古田キャンパス 東京経済大学 国分寺キャンパス |
| 神奈川県 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス |
| 新潟県 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 富山県 | 富山大学 五福キャンパス |
| 石川県 | 金沢医療技術専門学校 |
| 福井県 | 福井工業大学 福井キャンパス |
| 山梨県 | 桃源文化会館 山梨県流通センター(流通会館) |
| 長野県 | JA長野県ビル 松本歯科大学 |
| 岐阜県 | 岐阜大学 |
| 静岡県 | 日本大学国際関係学部(三島駅北口校舎) |
| 愛知県 | 名城大学 天白キャンパス |
| 三重県 | 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス |
| 滋賀県 | 比叡山高等学校 |
| 京都府 | 同志社大学 京田辺キャンパス |
| 大阪府 | 大阪経済大学 大隅キャンパス 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス |
| 兵庫県 | 神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス 神戸学院大学 有瀬キャンパス |
| 奈良県 | 奈良県コンベンションセンター |
| 和歌山県 | 県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 |
| 鳥取県 | 鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) |
| 島根県 | 島根県職員会館 |
| 岡山県 | 山陽学園中学校・高等学校 |
| 広島県 | 広島サンプラザ |
| 山口県 | 山口大学 吉田キャンパス |
| 徳島県 | 徳島大学 常三島地区 |
| 香川県 | 高松商工会議所 |
| 愛媛県 | アイテムえひめ |
| 高知県 | 高知中学高等学校 |
| 福岡県 | 九州産業大学 |
| 佐賀県 | 佐賀大学 本庄キャンパス |
| 長崎県 | 長崎県勤労福祉会館 長崎県立諫早技能会館 |
| 熊本県 | 熊本城ホール |
| 大分県 | 別府国際コンベンションセンター(ビーコンプラザ) |
| 宮崎県 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県建設センター 鹿児島県市町村自治会館 |
| 沖縄県 | 沖縄大学 本キャンパス |
- 記載された会場以外で受けることはできません
- 願書提出後は転勤や転居など受験者の事由による試験場の変更もできません
- 来場の際、車で周辺への駐車は禁じられています
- 一部、車での来場が可能な会場については受験票に記載されます
なお、試験会場へのアクセス方法も受験票に記載されますので、落ち着いて試験に臨めるよう、事前にしっかり経路を確認しておきましょう。
不測の事態が起きても遅刻することがないよう、時間に余裕を持って来場したいですね。
持ち物
- 受験票
- 筆記用具(BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、替え芯)
- 上履き、下履きを入れる袋(土足厳禁の試験場のみ)
- 腕時計1個(試験場に時計はありません)
※計算機能、通信機能等が付いているものや置き時計は使用不可
※懐中時計を机上に置いての使用は認められます
※事前にアラーム機能は解除すること - 鉛筆削り(ゴミが溜められる小さなものは可、電動鉛筆削りは不可)
- 問題用紙に用いる蛍光ペン(複数使用可)
- ハンカチ、ポケットティッシュ、目薬、点鼻薬
- 膝掛けや座布団は試験監督員の許可を受ければ使用可
注意事項・禁止事項
- 答案用紙の氏名、生年月日、受験番号が正しく記入やマークされていないと、欠席者とみなされ合格通知書が送付されません
- 試験開始30分を過ぎると受験できません
- 試験開始から午後2時30分までと、試験終了10分前は退出できません。午後2時30分までに退出した場合受験放棄とみなされ欠席者扱いになります
- 不正行為防止のため、電子機器類の使用は禁止です
(携帯電話等の通信機能があるもの、計算機能等が付いた腕時計や眼鏡など)
これらは配布される封筒に入れ、鞄等にしまいます。試験中の使用や、着信音、アラーム、
振動音が鳴ると不正行為とされ退場させられることがあります - 試験問題、答案用紙の持ち出し、持ち帰りは失格となります
- 試験時間中の飲食は、許可された場合を除き認められません。試験場によっては昼食をとれる場所がないので済ませてから来場しましょう
- 試験時間中、フードを含む帽子類の着用、耳栓の着用はできません。(本人確認が困難になる、不正行為の疑いになる為)傷病等で必要な場合は事前に試験研究センターに相談しましょう
- 試験場は禁煙です。指定場所以外の喫煙も禁止です
- 子供を同伴しての受験はできません
せっかく勉強したことが無駄にならないよう、注意事項をしっかり確認、準備して受験しましょう!
試験内容/配点/合格基準点
行政書士試験の試験内容と配点を一覧表にまとめてみました。
| 試験科目 | 出題形式 | 出題数 | 満点 |
| 法令等 | 5肢択一式 多肢択一式 | 40問 3問 | 160点 24点 |
| 記述式 | 3問 | 60点 | |
| 一般知識等 | 択一式 5肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 合計 | 60問 | 300点 | |
- 択一式 5肢択一式 1問につき4点
- 多肢選択式 1問につき8点
- 記述式 1問につき20点
また、合格基準点については以下の通りです。
- 「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」で244点中122点以上(満点の50%以上)
- 「行政書士の業務に関する一般知識等科目」で56点中24点以上(満点の40%以上)
- 全体の合計点数が300点中180点以上(満点の60%以上)
なお、試験問題の難易度により合格基準点が調整される年もありますので、この点も念のため頭に置いておいてください。
合格発表日


合格発表は試験翌年の1月下旬から2月上旬に行われます。発表方法は下記2つです。
- 行政書士試験研究センター事務所の掲示板に掲示
- ホームページに合格者の受験番号を都道府県ごとに掲載
また、2月上旬から中旬には合否・配点・合格基準点・得点が記載された合否通知書が申込住所に郵送されます。
その後、2月下旬には合格者に合格証送付される流れとなります。
まとめ


ここまで、行政書士試験の申込方法や試験日程、その他試験概要などについて解説してきました。
最後にもう一度、行政書士試験の申し込みから資格取得の流れをまとめておきますね。
| 日程 | 行事 |
| 7月第2週~ | 受験願書受け取り (郵送申し込みのみ) |
| 7月下旬~8月下旬 | 受験申し込み |
| 10月下旬 | 受験票送付 |
| 11月第2日曜日 | 試験日 |
| 1月下旬~2月中旬 | 合格発表・合否通知票送付 |
| 2月下旬 | 合格者に合格証送付 |
申し込みの準備は試験の3ヶ月前から始まります。
それまでに自信を持って試験に臨めるよう、逆算して勉強を進めましょう!