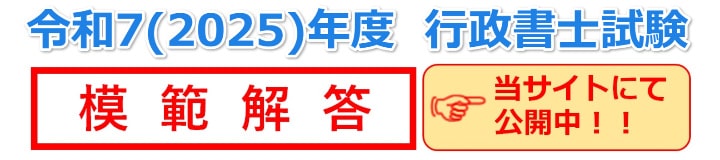行政書士は法律のスペシャリストとして知られていますが、実際にどのようなことが出来るのかまではご存じでない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、行政書士が出来ることや仕事内容等について掘り下げて解説していきたいと思います。
これから行政書士を目指される方や行政書士の仕事に興味がある方は、ぜひ参考にして下さい。
行政書士とは?


行政書士とは、簡単にいうと行政手続き・書類作成のプロフェッショナルです。
官公署、権利義務、事実証明に関する書類作成や提出手続きなどを行うことができる国家資格で、これらの書類は行政書士資格がないと作成提出することはできないようになっています。
会社を起業する際などに行政関連の書類を出す必要があるので、イメージ的には会社経営や社長などが主に必要だと思われますが、一般の方でも同じように提出しなければならない書類があります。
例えば以下のようなものが挙げられますね。
- 土地等に関する申請・手続き
- 自動車登録に関する書類作成
土地等に関する申請・手続きとは、田んぼや畑、農地の場所に家を建てる際などに必要になりますし、自動車登録に関する書類作成は自動車の新規登録、名義・住所変更、車庫証明、廃車手続きなどが挙げられます。(車屋が代理してくれる場合が多い)
このように、企業から一般の方まで様々な顧客からの依頼を引き受けるのが行政書士のメインの仕事になります。
また、重要書類の作成や手続きを行う行政書士資格ですが、意外にも資格保有者はそれほど多くはなく、R6.10月時点での保有者は約5万人となっています。
(出典:日本行政書士会連合会 会員数)
作成から相談まで幅広い業務に対してそこまで多くはないので、これから資格取得を目指される方でも遅くはないでしょう。
行政書士の仕事内容


行政書士がメインで行なう業務は大きく3つに分けられます。
- 官公署に提出するものなど書類作成業務
- 手続きの代理業務
- 相談業務
まず、大きな仕事として官公署に提出する書類の作成業務と手続きの代行が挙げられます。
こちらは簡単に説明すると、依頼主からの相談を受けて書類を作成・提出し、許認可を受けるというもの。
詳しくは後述しますが、行政書士のみが携われる業務範囲が法律で定められており、そういった書類の作成を行政書士資格保持者以外が行う事はできません。
行政書士の仕事内容の中で取り扱うことのできる書類の数は細かいものを含めるとじつに10,000種類を超えているので、かなり幅広く取り扱う仕事と言えるでしょう。
その他にも、個人で相談される方や会社を起業しようとする方も法改正後の細かなミスを防ぐために行政書士に相談するケースもあり、依頼主の内容によって作成・提出するものも変わってきますので、相談も重要な一つの業務です。
このように、行政書士とは国民と行政の間に入ってパイプ役として活躍出来る法律の専門家で、個人で作成するには難しい書類を作成し手続きなどを代わりに行うというのがメイン業務になってきます。
行政書士ができる仕事


前項で少し触れましたが、行政書士資格がなければ行うことができない独占業務というものがあり、資格がない人がしてしまうと法律違反になってしまうので注意が必要です。
行政書士の独占業務は大きく分けて3つあります。
- 官公署に提出するものなど書類作成業務
- 手続きの代理業務
- 相談業務
順番に解説していきますね。
官公署に提出する書類の作成
まず、区役所や市役所、各庁などの行政機関に提出する書類を、依頼主の代わりに作成する業務が挙げられます。
行政機関へ作成、提出する書類は許認可申請書類と呼ばれ、一般の方には非常に分かりずらいルールなどが多く存在するため、自身で作成するのは非常に困難です。
ですので、その道のプロである行政書士がその書類作成を代わりに行います。
権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類の作成・代行も独占業務のひとつ。
権利義務に関する書類とは、個人の権利や義務を守るために必要な書類のことで、権利の発生や存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示ができるものになります。
こちらも非常に複雑な内容の書類になるため、行政書士が書類の作成を代行することになります。
事実証明に関する書類の作成
事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書のことをいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、メインとなるものは、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、定款、各種議事録、会計帳簿、申述書などがあります。
特定行政書士を取得すれば業務の幅が広がる


上記で一部の独占業務を紹介しましたが、数多くのものが対象に含まれており、これらは行政書士資格がないと取り扱えません。この独占業務こそが将来的にも需要があると言われている点でしょう。
また、行政書士の中には特定行政書士と呼ばれる資格があり、研修をした後試験に合格すると認定を受けることができます。
特定行政書士は一般の行政書士資格ではできなかった行政不服申し立てに係る手続き(審査請求・再調査の請求・再審査請求)の代理業務が可能となります。
更に活躍の場を広げたいという方は、ぜひ特定行政書士にもチャレンジしてみて下さい!
意外と知られてない行政書士ができない仕事


上記で行政書士にしかできない独占業務について解説しましたが、逆に行政書士ができないことについてもご紹介したいと思います。
行政書士が関われる部分については法律の内容によって変わってくるのですが、他士業の独占業務となっているのものを業務としてやってしまうと法令違反となりますので注意が必要です。
ここでは3つピックアップして解説していきます。
- 訴訟に関する代理人
- 登記の申請
- 税務申告書の作成
順番に見ていきましょう。
訴訟に関する代理人【弁護士の独占業務】
弁護士には弁護士法で「訴訟に関する代理人」という独占業務があり、紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談、裁判手続きなど、紛争性のある事案については弁護士のみ相談・手続きなどが可能です。
行政書士は多くのトラブルに対する相談には乗れるものの、弁護士に比べると顧客に関われるレベルに差が出てきます。
訴訟という話になってくると基本的には行政書士の業務範囲外になってくるので、注意しておきましょう。
登記の申請【司法書士の独占業務】
司法書士の独占業務には「登記」というものがあります。登記とは、法に定められた規定の事柄を帳簿や台帳に記載することです。
会社設立の際の定款作成は行政書士でも行うことは可能ですが、登記申請は司法書士のみ行うことが可能で、会社設立において司法書士と提携して業務に当たらないといけません。
行政書士と司法書士で対応できる範囲が近いので間違える方もいるかと思います。
税務申告書の作成【税理士の独占業務】
税理士の独占業務は「税務申告書作成」です。
税申告に必要な会計帳簿は行政書士が作成することもできますが、税務申告を代理して行うことができるのは税理士だけとなっています。
このように業務範囲が被っている所でも、対応できる内容が資格によって変わってくるので注意しておきましょう。
まとめ
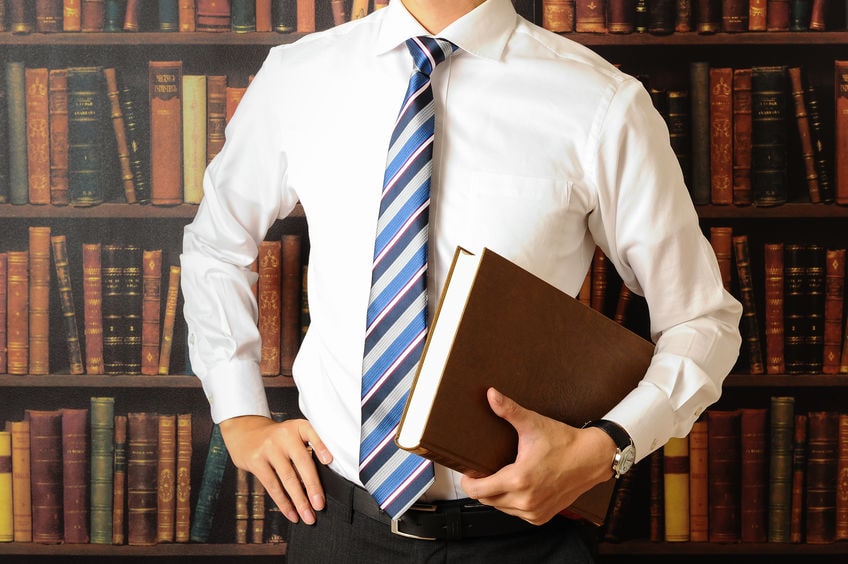
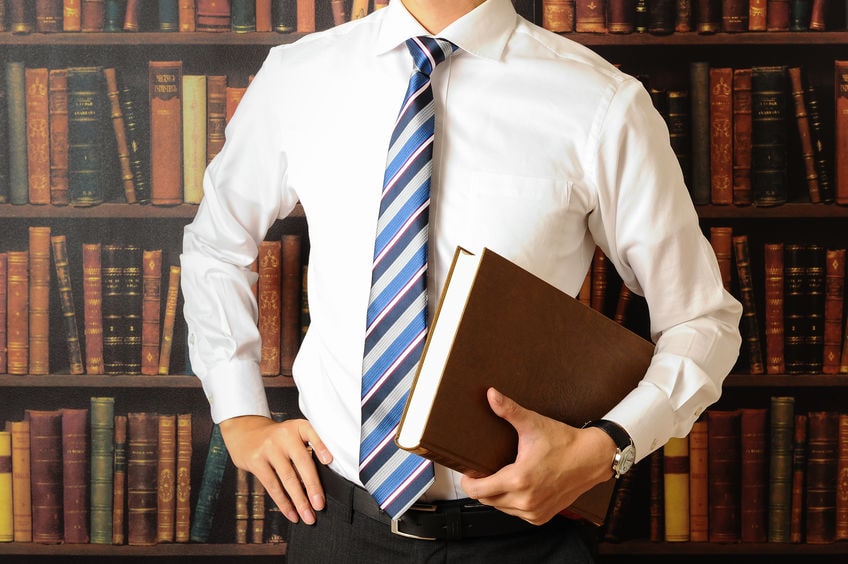
この記事では、行政書士の仕事内容やできること、できないことについてご紹介してきました。
個人や会社で行政に提出する書類を作成や手続きするのは非常に難しく、間違えてはいけない内容のものばかりですが、そういった書類作成や手続きなどを代わりに行ってくれるのが行政書士です。
行政書士は仕事面でも、法律で定められている独占業務によって業務範囲が決められていたり介入できる部分が違うので、今後も無くなるような仕事ではないでしょう。
独立開業することもできますし、会社に雇われていたとしても活躍できる場はたくさんあるので、自身のキャリアアップの為に取得しておくと幅が広がりますよ^^